この記事では、〈進行形〉を扱います。
「進行形」と言えば、「〇〇している」という訳し方が一般的ですが、他にも〈未来〉や〈反復〉などの意味も表すことをご存知でしょうか?
〈進行形〉には以下の用法があります。
- ある時点で進行中の動作
- 通常はしない一時的な動作・状態
- 確定した未来(近未来)
- 終点に向けた変化の途中
- 反復している動作
- 一定期間における繰り返し行為
- 行為の強調
- 話し手の不快感を表す
- 増減傾向
- 丁寧表現
この記事では、このような進行形の用法をかなり詳細にご紹介します。
進行形の用法について
進行形の用法10選
もう一度、進行形の用法を見てみましょう。
- ある時点で進行中の動作
- 通常はしない一時的な動作・状態
- 確定した未来(近未来)
- 終点に向けた変化の途中
- 反復している動作
- 一定期間における繰り返し行為
- 行為を強調
- 話し手の不快感を表す
- 増減傾向
- 丁寧表現
ここからは具体的に1つ1つの用法を見ていきましょう。
それぞれの用法の例文とワンポイント解説を載せていきます。
1. ある時点で進行中の動作
まずは最も有名な用法です。
進行中の動作He is playing the piano now.
彼は今ピアノを演奏している
進行中の動作They were playing the game then.
彼らはその時ゲームをしていた
この用法に関しては特に問題ないかと思います。
2. 通常はしない一時的な動作・状態
次に少し特殊な用法を見てみましょう。
一時的動作・状態He is wearing a tie today.
彼は今日は珍しくネクタイをしている
(いつもはネクタイをしていない)
一時的動作・状態I am living in Tokyo with my parents.
今は訳あって東京で両親と暮らしている
(普段は地方で一人暮らしをしている)
この用法の場合、
通常の習慣とは異なっていることが強調され、その動作・状態が長時間継続しないことが含意されています。また、liveなどのいわゆる
「進行形にできない動詞」でも『通常はしない一時的な動作・状態』を表す用法では使用することが可能です
。
3. 確定した未来(近未来)
英語には「未来時制」がない分、他の表現を代用的に使用します。その代用的な表現の1つが〈進行形〉です。
「英語には未来時制がない」というのは「時制=動詞の屈折(≒語尾変化)」と捉えた場合です。学説によってはwillなどを「未来時制」と見なす立場も存在しますが、ここでは立ち入りません。
確定した未来I am meeting Tom this evening.
私は今晩トムに会う予定だ
確定した未来The president is coming next month.
来月、大統領がやって来る
確定した未来We are leaving for London tomorrow.
私たちは明日ロンドンへ出発する
進行形が表す未来は〈確定した近い未来〉と呼ばれ、
比較的変更の余地がないとされています。また、進行形が未来を表す場合は、tomorrowなどの「未来を表す副詞(句)」が用いられ、使用される動詞は「移動」に関わる〈発着動詞〉が多いです。
関連記事:なぜ進行形は未来を表すことができるのか?
本来「進行中の動作」を表すはずの進行形ですが、なぜ「未来」を表現することができるのでしょうか?
詳しくは以下の記事でアニメーションを使って解説しています。
✔関連記事
【進行形】進行形が未来を表せる理由とは?
4. 終点に向けた変化の途中
「終点に向けた変化の途中」という説明は少し抽象的だと思うので、まずは例文を見てみましょう。
終点への変化途中The old dog is dying.
その老犬は死にかけている
(「死ぬ」という終点への過程を進行中)
終点への変化途中The sun is overlapping the moon.
太陽が月に重なりかけている
(「間もなく太陽が月に重なる」という読みもあり)
3.の
「確定した未来(近未来)」と似ているように感じられますが、3.の「確定した未来」は「終点(結果)」をフォーカスしているのに対し、こちらの4.の「終点に向けた変化の途中」は
「終点に到達するまでの変化の過程」をフォーカスしている点で異なります。また、この用法では、「
瞬間的に行為・動作が完了する動詞(≒瞬間動詞/点動詞)」が用いられます。
5. 反復している動作
「反復している動作」とは、日本語では「何度も〇〇している」と訳します。
反復動作She is jumping for the joy.
彼女は喜びのあまり何度も飛び跳ねている
(その瞬間、「飛び跳ねる」という動作が1回進行していたわけではない)
反復動作Someone was knocking the door outside.
誰かが外でドアをノックしていた。
(ノックの回数は1回ではなく複数回)
「1回の動作が瞬間的に完了する動詞」が用いられます。特に「wink(瞬きをする)」「jump(飛び跳ねる)」など、
身体に関わる動作がよく用いられます。
6. 一定期間における繰り返し行為
この用法では、必ず “these days”(最近)、“those days”(その当時) などの「期間」を示す副詞(句)が用いられます。
一定期間の繰り返し行為Tom is studying hard these days.
トムは最近一生懸命勉強をしている
一定期間の繰り返し行為I was coughing all night.
一晩中、咳き込んでいた
この『一定期間における繰り返し行為』が現在形として用いられた場合、他の用法の現在形とは次の点で異なります。すなわち、「
その言葉を発している瞬間にその行為が進行していなくても問題ない」ということです。例えば、”
Tom is studying hard now”という表現の場合は、その言葉を口にした瞬間にトムは一生懸命勉強していなければいけませんが、”
Tom is studying hard these days” という場合は、その発話の瞬間にトムは勉強している必要はありません。この違いを生む原因は、”
now”と”
these days”という副詞にあります。
英語という言語において、副詞が時制(テンス)や相(アスペクト)に与える影響は絶大的です。
7. 行為を強調
この用法は、特に話し言葉において頻繁に用いられます。
行為の強調Believe me. I am telling the truth.
信じてくれよ。本当のことを言っているんだ。
行為の強調Please be quiet. I am thinking.
静かにしてくれないか。今考えているところなんだ。
進行形の「まさにその最中なんだ」という意味合いが、その行為を強調してくれます。
8. 話し手の不快感を表す
この用法では、“always” や ”constantly” などの頻度の副詞が用いられます。
話し手の不快感He is always making silly mistakes.
彼はいつも馬鹿げたミスばかりしている
(それに対する話し手の不快感が込められている)
話し手の不快感They are constantly complaining.
彼らは毎度のように文句ばかり言っている
(それに対する話し手の不快感が込められている)
これに関しては、〈進行形〉の独立した用法というわけではありません。
“always” や
”constantly” などの副詞の力を大いに借りています。
9. 増減傾向
この用法では、“more and more” や “less and less” などの表現と共に用いられます。
増減傾向More and more women are continuing to work.
仕事を継続する女性が増えてきている
増減傾向Less people are smoking nowadays.
最近では喫煙する人は減ってきている
これに関しては、〈進行形〉の独立した用法というわけではありません。
“more” や “
less” などが持つ意味に大いに影響されています。
10. 丁寧表現
進行形の最後の用法です。
ご存知の通り、英語では進行形にすると「丁寧さ(ポライトネス)」が増すと言われています。
丁寧表現We are hoping that you will give us some advice.
私たちにいくらか助言をいただければと思っています
丁寧表現I was wondering if you could help me.
お力添えいただければと存じます
(↑過去形と組み合わせることで更に丁寧に)
進行形にすると丁寧さが増すのはなぜでしょうか?その理由は、「期待しているのは
この瞬間だけのことであって、あなたの反応次第では私の意見を変えますよ」と婉曲的に伝えているからです。進行形のポイントは、
「一時的ですぐに終了することが含意されている」ということです。もし仮に現在形で “
I hope that you will give us some advice” と言った場合は、「そう希望しているのは、過去・現在・未来の永続的です」という響きが混ざり、直接的な依頼となります。ちなみに過去形にすると更に丁寧になるのは、「あくまでそのようにして欲しい思っていたのは過去のことです」ということで更に間接的になるからです。
「一時性」が丁寧さを生み出すのは日本語でも同じ
英語では進行形にすることで「一時性」というニュアンスが生まれ丁寧さが増しますが、日本語でも同様な現象が起きています。
次の2つの例文を比べてみましょう。
普通お時間良いですか?
⬇
「一時性」で丁寧さ↑少しお時間良いですか?
日本語でも『少し』や『ちょっと』という「一時性」を表す表現があると丁寧さが増します。
英語でも日本語でも「丁寧さ」の本質は重なるところがあるのかもしれないですね。
進行形の用法のまとめ
以上で〈進行形〉の用法の説明は終了です。
今まで見てきた用法を再度おさらいしてみましょう。
- ある時点で進行中の動作
He is playing the piano now.
彼は今ピアノを演奏している
- 通常はしない一時的な動作・状態
He is wearing a tie today.
彼は今日は珍しくネクタイをしている(いつもはネクタイをしていない)
- 確定した未来(近未来)
We are leaving for London tomorrow.
私たちは明日ロンドンへ出発する
- 終点に向けた変化の途中
The old dog is dying.
その老犬は死にかけている
- 反復している動作
She is jumping for the joy.
彼女は喜びのあまり何度も飛び跳ねている
- 一定期間における繰り返し行為
Tom is studying hard these days.
トムは最近一生懸命勉強をしている
- 行為を強調
Believe me. I am telling the truth.
信じてくれよ。本当のことを言っているんだ。
- 話し手の不快感を表す
He is always making silly mistakes.
彼はいつも馬鹿げたミスばかりしている
- 増減傾向
More and more women are continuing to work.
仕事を継続する女性が増えてきている
- 丁寧表現
We are hoping that you will give us some advice.
私たちにいくらか助言をいただければと思っています
この記事を通して進行形の理解を深めていただけたら幸いです。
✔関連記事
【進行形】進行形が未来を表せる理由とは?
【進行形&文型】進行形にすると文型はどうなるのか?
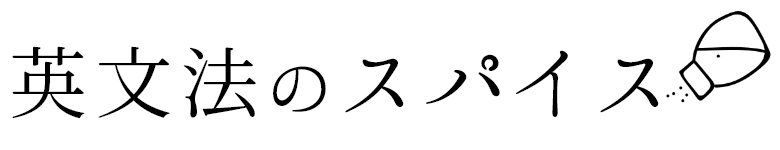


コメント
こんにちは。いつも本当にタメになる記事をありがとうございます。海外大学志望の高校生です。
突然ですが、最近文法で悩むことがあります。
① My father who lived in London cannot speaks English.
② My father lived in London cannot speaks English.
①My baby sleeping on the bed leaked poop.
②My baby who is sleeping on the bed leaked poop.
このように、関係代名詞による説明と、分詞による説明では同じ意味の英文が作れるのですが、ニュアンスの違いわかりません。
あと、否定の副詞が文頭に来たときになぜ倒置が起こるのかがわからないです…。否定の副詞を動詞の近くに置きたいからという説明を聞いたことがありますが、あれで正しいのでしょうか?なぜ倒置するのか、どう解釈すれば良いのでしょうか?
上記の文法事項をいつか扱ってもらえると嬉しいです…。
こんにちは。コメントありがとうございます。いつかは詳しい記事を作成してみようと思いますが、とりいそぎ簡単な説明をさせていただきます。
まず、「〈関係代名詞〉と〈分詞の後置修飾〉のニュアンスの違い」についてですが、非常に曖昧なのが正直なところです。
そうは言っても、ご用意いただいた2組目の例文を少し変えてみると、少し違いが見えてくるような気がします。
① Don’t touch the baby sleeping on the bed.
② Don’t touch the baby who is sleeping on the bed.
①では、一般論として「寝ている赤子に触ってはいけない」という意味合いが強く、その瞬間に目の前で赤ちゃんが眠っているとは限りません。
一方で、②では、「今現在寝ている目の前の赤ちゃんに触れてはいけない」という意味になるはずです。
このような意味の違いが明確になるケースは非常に限られていますが、「具体的に特定したい場合は②のように関係代名詞で修飾する」「具体的に特定しない(もしくは特定する必要がない)場合は①のように分詞で後ろから修飾する」と考えると良い気がします。
この回答にはあまり自信がないので、友人のネイティブスピーカーに聞いてみますね。
2つ目にご質問いただいた「否定の副詞が文頭に来た時に倒置が起こる理由」についてです。
理屈抜きにして「それっぽい説明」をするならば、「あえて通常の形から逸脱することで、読み手の注意をひくため」だと思います。疑問文ではないのに疑問文の語順を使うというのは、当然普通のことではありません。
これは、古文の「係り結びの法則」に似ているようにも感じます。通常では文末は終止形で終わるはずなのに、係り結びの法則では文末を連体形や已然形にします。その理由も「注意をひくため」です。書き手には「強調」や「疑問」や「反語」などの「強調したい何か」があるため、通常とは異なる形式(連体形や已然形)を用いることで、読み手に「あれ?おかしいな」と感じさせ、話し手が強調したい意図を汲んでもらおうとしているのではないでしょうか。私自身は「倒置は係り結びの法則と似ている」という捉え方をしています。
また、一般的に倒置が起こるのは書き言葉(文章)だけで、話し言葉ではその単語を強く発音することで強調します。このことからも、倒置は読み手の気をひくための文章上の工夫と言えると思います。
理屈の話をすると、「情報構造」という考え方が登場するのですが、それは今後記事にしますね。
いかがでしょうか。お役に立てていれば幸いです。
Instagramやメールなどでご連絡いただけると、返信も早くできるかと思います。海外大学を志望とのことで、これからもお力になれれば幸いです。
私の個人的な質問に、こんなにも丁寧に答えてくださって、本当にありがとうございます…。
関係代名詞が先攻詞を代名することで特定しているから、具合的に特定したい場合は関係代名詞による後置修飾ってことですかね…?
そう言われると「確かに…」とは思いますが、あまりスッキリしません…(すみません。丁寧にお返事いただいているのに…)。
以前通読した「一億人の英文法」にも、強調のために倒置が起きる(配置転換には感情がこもる)と書いてありました。やはり倒置が起こるタイミングはそこなんですね…。
情報構造と倒置の関係は、There is 構文みたいな感じですよね。旧情報から新情報へ流れる。
あれが関係するんですか…(あまりピンと来ていません……)。
記事、待ってます。
もし良ければですが、こういう「なぜ?」に答えてくれる文法書のおすすめなどがありますでしょうか…。学校の先生に聞いてもわからないことが多くて…。
今度もしわからないことが有れば改めてメールで質問をさせていただきます…。ありがとうございました。
いえいえ、あまり詳細に説明できず申し訳ないです。ご期待に添えるような記事をお届けできるように準備しますね。
「なぜ?」に答えてくれる文法書に関して、「大学入試英語のための文法書」というよりは「言語学の本」になってしまいますが、以下のようなものがおすすめです(正直、「大学入試英語で点数を取る!」ことだけが目標の場合はあまり相性が良くないかもしれません…)。
① 英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史
↑タイトルの通り、英文法の素朴な疑問を英語の歴史から紐解いてくれます。チャプターが細かく別れていて、とても読みやすいと思います。
②「英文法」を考える
↑従来の学校文法で「同じ意味」とされている文法事項(第3文型と第4文型の書き換え、能動態と受動態の書き換えなど)に対して、「そこには意味の違いがある」と主張し、「なぜ意味が違うのか?」を〈認知言語学〉という言語学の観点から解決しています。
③機能・視点から考える英語のからくり
↑言語の「機能」の側面から英文法の謎を解決しています(認知言語学も一部入っています)。「倒置と情報構造の関係性」や「関係代名詞の役割」など、先日のご質問と関連した内容も入っています。
②と③は、「アンチ学校文法」といった感じで、従来の学校文法の悪い点を指摘し、それの改善案を主張するといった内容がメインです。
付け足しをすると、英文法学習における「なぜ?」を解決するには、①「英語の歴史から考える(=歴史言語学)」②「人間の認知から考える(=認知言語学)」③「機能的な役割から考える(≒機能文法)」という3つのアプローチが有効的だと個人的に考えています。上の3冊は、まさにそれらのアプローチを採用しているものになります。
今後、英文法における素朴な疑問が浮かんだ場合は、上記の3つのアプローチのいずれかで解決できないかと考えてみると、上手くいくことがあるかもしれません。もちろんご質問もお待ちしています\(^o^)/