この記事では、〈対照言語学〉における日英語の動詞の性質を扱います。
タイトルやサムネイル画像にも書いてるように、

という衝撃的な命題を紐解いていきたいと思います。
はじめに
『そもそも〈対照言語学〉とは何か?』という説明から始めましょう。
今回の場合は、「2つ以上の言語」というのが「日本語と英語」になり、そして「相違点」の方に注目していきます。
〈対照言語学〉の詳細は、以下の記事で詳しく取り上げています。
例文をもう少し詳しく見てみると…
次の例文の(a)と(b)には意味の違いが隠れています。
(b) 私は昨日トムに電話をした。
(b) 私は駅へ歩いて行った。
(b) 私は水を沸かした。
(b) 私は彼女にここに来るように説得した。
ある操作を加えると…
「ある操作」とは、「逆接の内容を付け加える」というものです。
そうすると、英語の文だけ意味が通らなくなってしまうのです。
(b) 私は昨日トムに電話をしたが、彼は外出中だった。
(b) 私は駅へ歩いて行ったが、そこに到着しなかった。
(b) 私は水を沸かしたが、それ(水)は沸かなかった。
(b) 私は彼女にここに来るように説得したが、彼女は来なかった。
【結論】英語と日本語の意味が異なる理由
(a) 英語の文 「call」
この例文において、call という動詞には、「電話をする」という行為に加え、それによる目的が達成されたことまで含まれています。
「電話」をするという行為の目的とは何でしょうか?
それは、「相手と話すこと」です。
call という動詞には、「相手と話す」という目的が達成されたことまで含まれているから、
(a) *I called Tom yesterday, but he was out.
という相手と話すことが示されない文は不適切だと判断されます。
つまり、call という動詞を敢えて日本語で表記するなら、「相手に電話をかけ、電話越しに相手と話す行為」となるでしょう。
(b) 日本語の文「電話する」
それに対して日本語を見てみましょう。
日本語の「電話をする」という動詞は、ただ相手に電話をかけるだけで、その電話が繋がったのかどうかは問題ではありません。
この理由は先ほど述べたように、日本語は〈行為〉による目標の〈達成〉には無関心だからです。
つまり、「相手と話す」ということには必ずしも含意していません。
したがって、
(b) 私は昨日トムに電話をしたが、彼は外出中だった。
【まとめ】英語と日本語の動詞の性質
以上のことから、英語と日本語の動詞の性質に関して、次のように言われます。
しかしここで重要なのは、あくまで「多い」というだけで、全ての動詞が上記の性質に当てはまるという訳ではありません。
そこで次に英語と日本語の〈動詞〉における〈達成〉の度合いにおける分類を見ていきましょう。
〈達成〉の度合いの観点からの分類
この分類は、4つの場合が考えられます。
- 英語の動詞も日本語の動詞も〈達成〉を含む場合
- 英語の動詞も日本語の動詞も〈達成〉を含まない場合
- 英語の動詞だけが〈達成〉を含み、日本語の動詞は含まない場合
- 日本語の動詞だけが〈達成〉を含み、英語の動詞は含まない場合
1. 英語の動詞も日本語の動詞も〈達成〉を含む場合
この場合は、kill と「殺す」という動詞が挙げれます。
次の2つの文は、どちらも不適切と判断されます。
(b) *私は彼を殺したけど、彼は死ななかった。
英語でも日本語でも、kill と「殺す」という行為は、「その行為の目的=相手が死ぬこと」までを含んでいます。
2. 英語の動詞も日本語の動詞も〈達成〉を含まない場合
この場合は、leave と「出発する」が相当します。
(b) 彼は駅に向けて出発したが、そこに到着しなかった。
英語の leave も日本語の「出発する」も、arrive /「到着する」ということには無関心です。
つまり、「目的地への到着」の概念よりも「出発点からの出発」の方に関心が置かれています。
3.英語の動詞だけが〈達成〉を含み、日本語の動詞は含まない場合
この場合の代表例は上記の例文参照でたくさん見てきましたが、更にいくつか挙げておきます。
まず take と「写真を撮る」です。
(b) 私は彼の写真を撮ったが、撮れてなかった。
(b) の日本語は普通に日常会話でも使う表現です。
「写真撮ったけど、撮れてなかったよ」という表現は自然に聞こえるはずです。
あともう1つ挙げておきます。
それは、先ほどで出ましたが、‘boil’ と「沸かす」です。
特に日本語の「沸かす」について面白い発見があるので見てみたいと思います。
(b) 私は水を沸かしたが、沸かなかった。
(b) の方は特に違和感はないですが、少し手を加えると不自然な表現になります。
「水」を「お湯」に変えると、一気に適切さが怪しくなってきます。
この理由はなぜでしょうか?
それは〈目的語〉の種類にあります。
(b’)の「お湯」は、「沸かす」という動作の結果生まれた〈結果物〉
(b’)では、「沸かす」という行為の結果、完成した「お湯」という語が目的語になっているのに、後から「沸かなかった」という説明が続くのは違和感を感じるのです。
「目的語」と大きく一括りにされていますが、実は目的語は奥が深いのです。
4.日本語の動詞だけが〈達成〉を含み、英語の動詞は含まない場合
最後のパターンです、
驚くことに、この場合の代表例は存在しないのです(少くとも私は思い浮かびませんでした)。
読者の方は何か思いつきましたか?
「日本語はあいまいな表現が多い」とよく言われることがありますが、このことからもよく分かる気がします。
以上が「達成度の度合い」から見た英語と日本語と英語の動詞の比較でした。
【応用編】英語で〈行為〉のみを表したい場合
ここでもう一度最初の文に戻ってみましょう。
「私は昨日トムに電話したが、彼はその時外出中だった」
という意味で
(a) *I called Tom yesterday, but he was out.
と書くと不適切だということを説明しました。
というのも。英語の call という動詞は、「相手に電話をかけて、電話越しに話をする」という「行為+結果」を表すからです。
それでは「私は昨日トムに電話したが、彼はその時外出中だった」と英語では表現できないのでしょうか?
もちろんそんなことありません。 英語でもしっかり表現することはできます。
そんなときに使用するのが try to V です(Vは動詞の原形を表します)。
この適切な表現になります。
英語で元々〈行為〉と〈達成〉まで含んでしまっている動詞から、〈達成〉の意味を取り除き、〈行為〉の意味だけにしたい時は、try to V の力を借りるということです。
try to V の捉え方
このように考えてみると、try to V の捉え方が今までと少し変わってくるような気がします。
try to V は 〈to 不定詞〉の分野よりも、〈助動詞〉の分野に近いような気がします。
なぜなら、動詞に意味を付け足しているからです。
もっと正確に言うならば、動詞に「マイナス達成」という意味を付け足しているのです。「マイナスを足す」という数学的な発想です。
〈義務〉を付け足す〈助動詞〉として have to V があるように、
〈マイナス達成〉を付け足す助動詞 try to V があると見てあげることは可能なはずです。
しかし、実際の学校文法ではこのような解釈はなされていません。
それはなぜでしょうか?
最後に少しそのことに触れて終わりにしたいと思います。
学校文法の姿
なぜ学校文法で try to V を〈達成〉を取り除く助動詞として定義しないかという理由は、個人的に2つあると思っています。
1つ目の理由
まず1つ目は、学校文法では〈助動詞〉は、
- 何かしらの〈義務〉や〈推量〉を表すもの
- どんな主語が来ても形が変わらないもの
という制約が蔓延しているからだと考えます。
‘try to V’ は確かに〈義務〉や〈推量〉を示さない上に、3単現のsの影響をもろに受けます。
そんな部外者である try to V が、わざわざ will や can などの絶対王者に対して、道場破りしてまで助動詞の仲間入りをする必要があるかと言われたら、確かに無いように思えます。
その証拠に、〈進行形〉の be や〈完了形〉の have だって実は〈助動詞〉ですが、
- 何かしらの〈義務〉や〈推量〉を表すもの
- どんな主語が来ても形が変わらないもの]
という特徴を持っていないので、学校文法では〈助動詞〉と扱われていません。
参考記事:【助動詞】助動詞の種類・分類について
2つ目の理由
2つ目の理由としては、try という動詞には
だと思います。
もし仮に try to V だけを〈助動詞〉に分類すると、try Ving の扱いが難しくなってしまいます。
そう考えると、try to V だけを〈助動詞〉に分類するのではなく、remember to V と remember Ving などの「to不定詞と動名詞で意味が違う動詞」という項目で登場させた方が遥かに扱いやすいことが分かります。
以上が try to V を〈助動詞〉として見なさない2つの理由だと考えています。
タイトル
- will や can などの有名な助動詞とあまりに性質が異なるから
- try Ving という動名詞表現の存在があるから
分類文法としての学校文法
学校文法で ‘try to V’ が〈助動詞〉として扱われない理由を見てきましたが、
このように見てくると、学校文法=〈分類文法〉と言い換えることができそうですね
(分類文法というのは私個人の造語なので学問用語ではないことをご了承ください)。
を考えて分類されたのが、学校文法、即ち〈分類文法〉だということです。
さっきの〈完了形〉の have が本当は〈助動詞〉なのに、〈助動詞〉として扱われないのもそのせいだと思います。
その観点から学校文法を眺めてみると今までと違った姿が見えてきそうです。
色々と【応用編】の中で余談が入ってしまいましたが、
〈マイナス達成〉を付け足すという立派な役割をもっている try to V に学校文法では光が当てられないという可哀想な背景を見てきました。
この記事を読んだそんなみなさんは、是非ともこれから try to V に光を当ててやって下さい。
少し長くなってしまいましたが、【応用編】はこれにて終了です。
全体のまとめ
今回は、〈対照言語学〉という考え方に基づいて、英語の動詞と日本語の動詞を比べてきました。
一見すると全く同じ意味に思える動詞の組み合わせでも、実は違う意味を持っているのです。
そして、その意味の違いを生み出す原因は、〈達成〉の度合いです。
今回の記事を一言でまとめるなら、
ということに尽きるかと思います。
【参考文献】
- Radden & Dirven (2007), Cognitive English Grammar, John Benjamins Pub Co.
- 池上嘉彦 (2016)『〈英文法〉を考える』ちくま学芸文庫
- 鈴木孝夫 (1973)『ことばと文化』 岩波新書
最後に
今回の投稿は、「call = 電話する」と覚えることを批判したり、揶揄する意図は一切ありません。
英語を学習して間もないころの「意味の違い」に対する豊かな感受性や好奇心を思い出していただきたい、というのがこの投稿に込めた1つの思いです。
ほんのわずかな意味の違いだとしても、時には微々たる意味の違いという追憶の糸を繰り、初々しく、瑞々しい英語を学習して間もないあの日の萌芽に遅ればせながらも陽の光を当ててあげるのも、なかなか悪くはないはずです。
そんな若返りのスパイスを少しでもみなさんの心に振りかけることができていたら、この記事を書いて良かったなと、心の底からそう思えます。
今回もご覧頂きありがとうございました。
また次の記事でお会いしましょう。
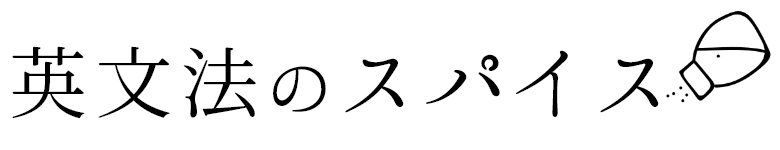



コメント