この記事では、『that節とto不定詞の書き換え』について扱います。
いわゆる〈繰り上げ構文〉と言われるものです。
② I believe that Tom is honest.
③ I believe Tom to be honest
結論:意味の違いは?
早速ですが、この3つの例文における意味の違いを説明します。
② I believe that Tom is honest.
③ I believe Tom to be honest
これら3つの例文における意味の違いは、〈直接性〉の違いです。
① SVOCの第5文型
まずはこちらの例文
文構造としては、SVOCの第五文型になります。
〈直接性〉とは、主語がその出来事に対してどれくらい直接的に関与しているかの度合いのこと
私は彼の正直な振舞いを私は何度も見てきました。
そんな私はある人に次のような質問をされました。
「トムって正直なのかな?」
そんな時に自信をもってこう答えます。
‘I believe Tom honest’
② that節
次にこちらの例文
この例文は、〈直接性〉が弱い(つまり〈間接性〉が強い)表現です。
〈直接性〉が弱いというのは、主語の「私」が「トムが正直である」という事態へ間接的に関与しているということです。
次のような場面をイメージしてみましょう。
彼についてはあまり知らないのですが、
私の友人Aからは「トムは正直だよ」だと聞かされています。
そんな私はある友人Bに次のような質問をされました。
「トムって正直なのかな?」
私は友人Aからの言葉を参考にこう答えます。
‘I believe that Tom is honest’
「私」は直接トムの正直な振舞いを見てきたわけではなく、友人Aからの情報によって「トムは正直である」と信じています。
したがって、「トムは正直である」という事態に間接的に関与していることになります。
補足情報
There is a possibility that Tom may be not an honest person.
(トムが正直者でないということもあり得る)
③ to不定詞
最後にこちらの例文
構文としては、補語に〈to 不定詞〉が置かれています。
〈直接性〉のまとめ
ここで3つの例文についてまとめます。
- I believe Tom honest ⇒〈直接性〉が最も強い
- I believe that Tom is honest. ⇒〈直接性〉が弱い
- I believe Tom to be honest. ⇒〈直接性〉が中間
3つの例文は、〈直接性〉の強さに違いがあることが分かります。
そこで、ここからは〈直接性〉の大小関係が生じる理由を考えていきたいと思います。
① SVOCの第5文型の〈直接性〉
この構文の〈直接性〉が最も強い理由は、‘Tom’ の〈格〉にあります。
この構文では、‘Tom’ は〈目的格〉になっています。目的格〉というのは、動詞 ‘believe’ の目的対象であり、その動詞の影響を強く受けています。
そして、その ‘believe’ という動詞の影響を受けるということは、必然的にその〈行為者〉である「私」の介入も強くなり、その結果、主語である「私」の「トムが正直である」という事態への〈直接性〉も強くなる、と考えられます。
このように名詞の〈格〉に注目すれば、〈直接性〉の違いも説明できてしまいます。
同じように次の②の例文についても考えてみましょう。
② that節の〈直接性〉
この構文の〈直接性〉が弱い理由は、‘Tom’ が〈主格〉であることに起因します。
‘Tom’ が〈主格〉であるということは、‘Tom’ は動詞 ‘believe’との結び付きよりも、述語 ‘is honest’ との結び付きの方が強く、‘Tom is honest’ という〈節〉を形成しています。
つまり、‘believe’ との結びつきが弱いということは、〈行為者〉の「私」による介入も弱く、その結果、「私」の「トムは正直である」という事態への関与は直接的になり、〈直接性〉は弱くなる、と考えられます。
今回は ‘Tom’ が〈主格〉として、〈節〉を形成していることがポイントです。
〈節〉が形成されると、そこで1つの頑丈なカタマリが生まれるというイメージです。
③ to不定詞の〈直接性〉
残るはこちらの例文
構文としては、補語に〈to 不定詞〉が置かれています。
(1) to不定詞 の捉え直し
まず〈to 不定詞〉の認識を改める必要があります。
この分析は、今回都合良く話を進めるために、筆者が勝手に定義したわけではありません。
実際に英語学で、〈to 不定詞〉は〈節〉を形成すると定義されているのです。
どのように解釈すれば、〈to 不定詞〉も〈節〉を形成すると分析するのでしょうか?
そのためには、〈節〉の定義を見直してみましょう。
この定義には問題はありません。この定義を拡張すれば、〈to 不定詞〉も〈節〉を形成すると考えることが可能です。
「主語と動詞が揃っている」という説明を聞いて真っ先に思い浮かぶのが、
これが一番有名な〈節〉かと思います
しかし、次の例文の下線部も〈節〉なのです。
「私はトムが医者になることを望む」
和訳の方を見れば分かりやすいと思いますが、「トムが医者になる」の部分に主語と動詞がしっかり存在していますね。
これも一種の〈節〉と見なせるわけです。
つまり、先ほどの
という定義における主語と動詞は、
「私はトムが医者になることを望む」
・’I am proud of being a doctor’ 「私は医者であることを誇りに思う」
→ ‘I am proud of my(me) being a doctor’ 「私は私が医者であることを誇りに思う」
・Turning off the light, I went to bed. 「電気を消して、私は床に就いた」
→ I turning off the light, I went to bed. 「私は電気を消して、私は床に就いた」
以上の例文からも、〈準動詞〉も〈節〉を形成すると分析できます。
〈準動詞〉が形成する〈節〉のことは〈非定形節〉と呼ばれ、一般的に知られる ‘that節’ などは〈定形節〉と呼ばれるもので、両者は全く同じ種類の〈節〉と見なされるわけではありません。
(2) 直接性が中間になる理由
前置きとして〈to 不定詞〉の説明が長くなりましたが、ここから〈直接性〉が中間になる理由を考えていきます。
今まで説明してきたことが全部ここで繋がります。
次の3つのポイントを思いだしてください。
これら3つを合わせれば、次のように言えます。
そして、ここからは不等式を考えていきます。
① = SVOCの第5文型
② = that節(定形節)
③ = to不定詞(非定形節)
と置き換えると、
⇒ ③>②
⇒ ③<①
となって、
① ‘I believe Tom honest’
③ ‘I believe Tom to be honest’
② ‘I believe that Tom is honest’
というように、③の〈直接性〉の度合いは中間になるということです。
だいぶ長い説明になってしまったので、何度か読み返して頂きたいです。
他の例文について
今まで〈直接性〉の大小関係を見てきましたが、他の例文も紹介しておきます。
find 構文
② I found that this cake is delicious.
③ I found this cake to be delicious.
この例文でも、’believe’ の構文で確認した〈直接性〉の大小関係は成立します。
すなわち、①>③>②という順番です。
それぞれのニュアンスや使われる場面は以下のようになります。
⇒〔直接性〕「私」の事態への関与が直接的
⇒〔直接性〕「私」の事態への関与は間接的
see 構文
〈知覚動詞〉の ‘see’ では、他とは変わった面白い現象が起こります。
② I saw that Tom was angry.
② 私はトムが怒っていると分かった(思った)。
‘see’ の「思う」への意味拡張について
私はトムが怒っていると分かった(思った)。
比較
私はトムが怒っているのを見た。
認知心理学の観点からしても、人間というものは視覚重視で、耳や鼻などの他の器官よりも目から入ってくる情報の方が圧倒的に多い生物です。認識や思考の約90%以上を目からの視覚情報を頼りに生成しているとも言われています。そんな人間が生み出す言語において、’see’ という視覚認知を表す動詞が「思う」という認識・思考を表す動詞としても機能するようになったと考えることができそうです。
②「分かる」という〈間接知覚〉(精神知覚とも呼ぶ)
【日英比較】日本語における〈直接性〉
ここからは、【日英比較】のお話をしたいと思います。
今までずっと〈直接性〉について長々と説明してきましたが、日本語でもその〈直接性〉の概念が存在するのです。
日英比較①
まずはこの例文に対応する日本語を考えます。
(b) I believe that Tom is honest.
(b’) 「私は彼を恋しいと思う」
(a’)は、「彼が恋しい」という気持ちに対して、直接的で強い気持ちが表れています。
その一方で(b’)は、「彼が恋しい」という気持ちを、一歩引いて客観的かつ冷静に感じています。
⇒「恋しい」という形容詞が、連用形になり直接「思う」という動詞に繋がるから
⇒「恋しい」という形容詞が、終止形になり一旦文が完成した状態で「思う」という動詞に繋がるから
「恋しい」という形容詞の活用形が異なると、〈直接性〉の違いが生じるのです。
ちなみに、(b’) の「終止形になり一旦文が完成した状態」というのは、英語のthat節の中が1つの文として完成しているのと同じ理屈だと分かりますね。英語でも日本語でも、終止形が括られた節が存在すると、〈直接性〉の度合いが下がるということです。
日英比較②
次にこちらの例文に対応した日本語を考えます。
「私はトムが怒っているのを見た」
(b) I saw that Tom was angry.
「私はトムが怒っていると思った」
(a) では ‘see’ は「見る」の意味を示しているのに対して、(b) では ‘see’ は「思う」の意味を示しています。
これと似た現象が日本語の「見る」と「思う」の語法でも見て取れます。
英語では、that節で内容が1つの文として括られると、’see’ は「思う」という意味になりました。
この「that節で内容が1つの文として括られる」というイメージは、日本語における終止形のイメージと同じです。
そして、「思う」という動詞は終止形のカタマリだけに後続するのです。
○「私はトムが[怒っている]と思った」
○「私はトムが[怒っているの]を見た」
〔例文参照〕「事故が起こるのを防ぐ」→「事故が起こることを防ぐ」
国文法の話も出てきて少し話が複雑になってしまいましたが、
英語と比較することで、母語の日本語について新たな発見を与えてくれる
全体のまとめ
今回は、〈繰り上げ構文〉と呼ばれる例文を比較して、〈直接性〉が引き起こす意味の違いを見てきました。
その意味の差異は形式の差異から説明できるということが重要です。
そして、その意味の差異には人間の思考や認知が反映されています。
英文法を学習すると、人間の世界の切り取り方を垣間見ることができます。
これも英文法のスパイスです。
人間がどのように世界を捉えているのか気付くことができる
ポイントをまとめておきます。
- 形式が異なれば意味も異なる
- 〈直接性〉の概念は英語にも日本語にも存在する
- 〈準動詞〉とは、〈to 不定詞〉〈動名詞〉〈分詞〉の3つを指す
- 〈準動詞〉も〈節〉を形成すると分析される
- 〈知覚動詞〉には、〈直接知覚〉と〈間接知覚〉の2種類がある
〈知覚動詞〉〈直接知覚〉〈間接知覚〉
〔参考文献〕
- Bolinger, Dwight (1977), Meaning and Form, Longman High Education.
- Radden & Dirven (2007), Cognitive English Grammar, John Benjamins Pub Co.
- 池上嘉彦 (2016)『〈英文法〉を考える』 ちくま学芸文庫
- 三原健一 (2008)『構造から見る日本語文法』 開拓社
今回もご覧頂きありがとうございました。
また次の記事でお会いしましょう。
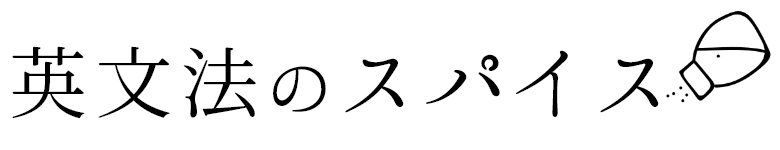
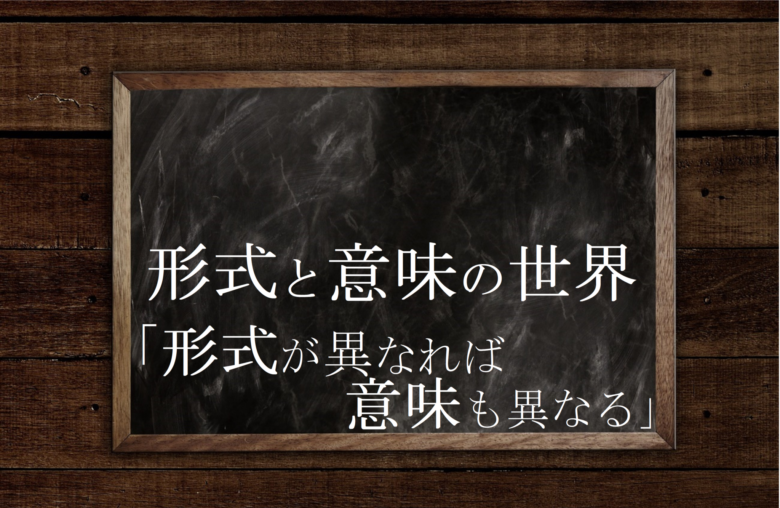

コメント