そんな説明を学校の英語の授業で聞いたことはないでしょうか?
実際に次の2つの例文は、学校英語では「thatが省略されているかどうか」の違いだと言われています。
(b) I think it will rain tomorrow.
しかし、実はこれらの2組の文は「意味が異なる」とする言語学の立場も存在するのです。
今回は、そんないわゆる「接続詞のthatの省略」と呼ばれる現象にスポットを当て、「形式が異なれば意味も異なる」ということを説明していきたいと思います。
参考書籍
今回の記事で扱う内容は、以下の書籍を参考にしています。
著者は東京大学の名誉教授の池上嘉彦先生です。
この記事の内容は、あまり耳にする内容ではないため、信憑性に欠けるように感じれるかもしれませんが、しっかりと文献に則っていることをご理解ください。
that の有無による意味の違い
本題のテーマに対する結論をお話します。

英語の「情報」について
『接続詞thatの有無で意味が異なる』というトピックに必要になってくる英文法のアイデアについてお伝えします。
そのアイデアとは、〈旧情報〉と〈新情報〉というものです。
〈旧情報〉と〈新情報〉について
英語という言語にかかわらず、言語を使用するとき、
- 話し言葉なら、〈話し手〉と〈聞き手〉の間で
- 書き言葉なら、〈書き手〉と〈読み手〉の間で
多種多様な情報が飛び回っています。
そんな情報を、
- 「話題として既に登場したか、してないか」
- 「話し手と聞き手で共有できているか、できてないか」
の観点から線引きすることができます。
そして、次のように定義されます。
まずはこの知識を押さえておきましょう。
これで下準備は終了です。>あとは『接続詞のthat』と関連させながら理解を深めていきましょう。
接続詞のthatの有無による意味のちがい
ここから本題に入っていきます。
接続詞の that が有る場合と無い場合の意味の違いについてですが、
という察しは付くかと思います。
まさしくその通りです。
それでは、’that’ がある場合は、〈旧情報〉か〈新情報〉のどちらでしょうか?
正解は、
もう一度先ほどの例文を見て、もう少しく説明していきたいと思います。
(b) I think it will rain tomorrow.
(a) that がある場合
しかし、外を見てみると、雲行きがなんだか少し怪しそう。
そこで花子が太郎に、「明日の天気どうなると思う?」と聞きました。
太郎は「せっかくのデートだけど雨になりそうだ」と思って、
深いため息をついて一言、
‘I think that it will rain tomorrow.’
この設定だと、花子の「明日の天気どうなると思う?」という言葉によって、「明日の天気」という話題が既出・共有の状態になりました。
だからその問いに答える太郎は、‘I think that it will rain tomorrow’ と答えたということです。
that節中の内容が〈旧情報〉であることが分かると思います。
(b) that がない場合
しかし、花子と太郎の間には気まずい沈黙の状態が続いています。
そんなとき太郎がふと窓の外を見てみると、空にどんよりと重たい雲が。
太郎は「この気まずい沈黙を打ち破るチャンスだ!」と思って、
ボソッと一言、
‘I think it will rain tomorrow.’
この設定だと、太郎と花子の間には「明日の天気」という話題はおろか、何の話題も上がっていません。つまり、〈旧情報〉は一切存在していないのです。
これから口にする情報全てが〈新情報〉です。
そんな沈黙を打破するべく、「明日の天気」という〈新情報〉を話のネタとしようとした太郎は、
まとめ
以上のように、‘that’ の有無による使われ方の違いを見てきました。
実際にどのような場面で ‘that’ を使い分けるか想像できたでしょうか?
冒頭で、以下の2つの文の意味は異なるということを言いました。
(b) I think it will rain tomorrow.
これに追加して正確に言うならば、
ということになります。
接続詞の that の有無が、後ろに続く情報が〈旧情報〉か〈新情報〉なのかということに関係しています。
接続詞thatと同じ振る舞いをする文法事項
ところで、次のような感想を抱きませんか?
接続詞のthat と同じ振る舞いをする文法事項が存在します。
それは、〈定冠詞〉の the です。
〈定冠詞〉の the は〈旧情報〉である〈名詞句〉の前につきます。
一応例文で確認してみましょう。
The old man went to a mountain…
「昔々あるところに、お爺さんとお婆さんが住んでいました。お爺さんは山に芝刈りに…」で有名な昔話の英訳です。
1文目で ‘an’ が付いていたのが、2文目では ‘the’ になっていることがポイントです。
2文目では、’old man’ は〈旧情報〉になっているので ‘the’ が付きます。
このように、〈定冠詞〉の ‘the’ と〈接続詞〉の ‘that’ は非常によく似た使われ方であることが分かります。
しかし、これは偶然ではなく、理由が存在します。
この謎を解明するために、〈英語史〉という知識を借りたいと思います。
〈英語史〉を見てみると…
〈英語史〉とは言うまでもなく、英語の歴史のことですが、〈定冠詞〉の ‘the’ と〈接続詞〉の ‘that’ の歴史を遡ってみると、面白い事実が明らかになります。
その事実とは、
〈定冠詞〉の the と〈接続詞〉の that が同じ振る舞いをするのは、元々は同じ親元から発達してきたからだったんです。
〈指示代名詞〉の ‘that’ という同一の親元か生まれたその2つは、
- 〈定冠詞〉の the は〈名詞〉に対して〈旧情報〉を付加する者として、
- 〈接続詞〉の that は〈節〉に対して〈旧情報〉を付加する者として、
それぞれ別の役割をもって発達してきたのです。
英文法を学習すると、思ってもいなかった繋がりに出会うことができるんです。
無関係に思える現象が相互に結び付いていることに気付くことができる
本当に英文法って奥が深いとつくづく実感させられます。
【日英比較】日本語における〈旧情報〉と〈新情報〉
さてここで、いつもお馴染みの英語と日本語の比較に移りたいと思います。
さきほど、英語では〈旧情報〉を〈定冠詞〉の the や〈接続詞〉の that が表していると説明しましたが、日本語でも似たような現象が起きています。
日本語の〈旧情報〉と〈新情報〉を表す文法、
それはずばり、助詞の「は」と「が」です。
例として、次の2つの文が使われる場面を想像してみましょう。
例文
1.「僕は太郎です」
2.「僕が太郎です」
この2つの例文をそれぞれ確認していきましょう。
1. 「僕は太郎です」
まずはこちらの例文
どんな場面で使用されるでしょうか?
これは、ある人が「あなたの名前は何ですか?」と聞かれた時に返す言葉です。
つまり、この質問をした人の目の前に「あなた」がいるはずなので、「僕」という人物は共有された情報、即ち〈旧情報〉になります。
そしてその〈旧情報〉の後に助詞「は」が置かれています。
2. 「僕が太郎です」
次にこの例文
この例文は、「太郎くんはどの人ですか?」と聞かれた時に返す言葉です。
つまり、太郎という人は存在する前提なので「太郎」という人物は共有された情報、即ち〈旧情報〉です。
言い換えると、「僕が」の方が〈新情報〉であることが分かります。
その〈新情報〉には助詞「が」が付いています。
もう少し実感するために…
先ほど日本語における〈旧情報〉と〈新情報〉の区別を見てきました。
そして、本当にどちらが〈旧情報〉なのか実感する方法が存在します。
その方法とは、〈旧情報〉を省略してみることです。
実際に上の2つの例文で〈旧情報〉の部分を省略しても意味は通じます。
→「
→「僕が
このことからもどちらの部分が〈旧情報〉なのか判断できますね。
日本語の〈旧情報〉と〈新情報〉のまとめ
ここで日本語の分析をまとめておきます。
日本語において、
こんな感じで、実は母語である日本語にも〈旧情報〉と〈新情報〉の区別の概念があります。
英語を勉強していると、〈不定冠詞〉と〈定冠詞〉の使い分けに苦戦することがあるかと思いますが、
日本語にも同じような難しさが潜んでいたんですね。
日ごろ日本語を使うときに、
〈新情報〉のときは「が」を使う
と意識的に使い分けてる方はいないかと思いますが、こうして意識的に光を当ててみると面白い発見に出会えます。
こうした母国語である日本語について新たな気付きを与えてくれるのも、英文法のスパイスの1つです。
英語と比較することで、母語の日本語について新たな発見を与えてくれる
全体のまとめ
今回の全体のまとめをして終わりにしたいと思います。
学校英語の「接続詞のthatは省略できる」という説明にスポットを当てて、実は that の有無で使われる場面が違うということを説明してきました。

その中でみなさんがよく知る〈定冠詞〉the との関連性と、母国語である日本語における〈旧情報〉と〈新情報〉の表し方にも触れました。
今回のポイントです。
- 情報は〈旧情報〉と〈新情報〉に分類できる。
- that がある場合は〈旧情報〉、ない場合は〈新情報〉を引き連れる。
- 〈接続詞〉の that と 〈定冠詞〉の the は同じ機能をもっている。
- 日本語における〈旧情報〉は「は」、〈新情報〉は「が」が示す場合が多い
〈定冠詞〉〈不定冠詞〉〈英語史〉
特に〈旧情報〉と〈新情報〉は他の文法事項にも応用できるので、覚えておくと役に立つアイデアです。
✔関連記事
【存在文】旧情報と新情報の観点から考える there is 構文
【参考書籍】
- Bolinger, Dwight (1977), Meaning and Form, Longman.
- Radden & Dirven (2007), Cognitive English Grammar, John Benjamins Pub Co.
- 池上嘉彦 (2016)『〈英文法〉を考える』 ちくま学芸文庫
今回の記事が面白いと思っていただけた方は、この書籍をおすすめします。ぜひお手にとってみてください。
最後に
今回、学校文法で「接続詞のthatの省略」という説明がなされてきたことに対して、実際は「省略」という「形式」の現象ではなく、「意味」の違いが存在するということをお伝えしてきましたが、学校文法でなされている説明を頭から否定するつもりはありません。
というのも、教育の現場では、「意味」の差異を教授するのは非常に難しいことです。なぜなら、「意味」とは非常に抽象的であり、個人差があるからです。
そのような言語の性質を踏まえると、学校英語が「形式」に焦点を当てることになってしまうのは仕方がないことだと思っています。
このサイトでは、一般的になされている説明を引き合いに出すことが多いですが、決してその説明を否定するわけではなく、あくまで「1つの提案」としてアイデアを発信することに努めていきます。
このサイトを見て、少しでも多くの方が英文法の魅力に心惹かれ、
日々の英語学習にスパイスが振りかかかることを心から願い、
今後もアイデアを発信していきたいと思っています。
今回もご覧頂きありがとうございました。
また次の記事でお会いしましょう。
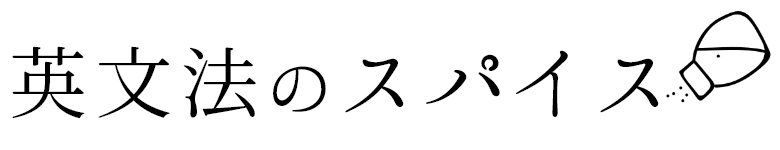


コメント
Too complicated. Both are totally interchangeable.
Hope you take it as one view.
Thanks, teacher.