英語の「使役動詞(causatives)」といえば、make / have / let などが代表的です。
これらは日本語では「~させる」と訳されることが多いので、「全部同じ意味じゃないの?」と思いがち。
しかし、使役動詞の選択 は、話し手と相手(行動を起こす人)の関係性や、行動を“強制している”のか、“依頼している”のか、“許可を与えている”のか、といった微妙なニュアンスを大きく変化させます。
たとえばビジネスシーンで上司が部下に仕事を任せるなら have が自然、子どもに何かを無理にやらせるなら make がしっくりくるかもしれません。一方、相手がやりたがっていることを「やっていいよ」と後押しするなら let を使うのが最適です。
こうした違いを理解せずに、とりあえず全部「~させる」という感覚で使ってしまうと、相手に対して意図しない“強制的”な響きを与えたり、逆に“許可”のニュアンスが伝わらなかったり といったコミュニケーションのすれ違いが起きるリスクがあります。英会話のスムーズさや文章の的確さを高めるためにも、3つの使役動詞がそれぞれ何を強調しているのか を押さえておくことはとても大切です。
本記事では、まずは「使役動詞とはどんなものか」という基本的な構造と、肯定文でのニュアンスの違いについて解説します。
短い例文や具体的なシーンを通じて、なぜ make は「強制的な印象」が強く、have は「依頼・任務としての自然なイメージ」があり、let は「許可」や「自由度の高さ」を感じさせるのかを確認していきましょう。
まずは使役動詞(make, have, let)の基本イメージを知ろう
英語の使役動詞といえば、make / have / let がよく取り上げられます。いずれも日本語に訳すと「~させる」となるため、一見同じように思えるかもしれません。しかし実際には、それぞれがもつ「相手を動かす力」や「相手に与える許可の度合い」が異なるのです。
ここでは、まず肯定文での使い方をざっくりとおさらいしましょう。
使役動詞は相手にアクションを起こさせる動詞
make, have, let はいずれも [主語 + 使役動詞 + 目的語 + 動詞の原形] の形をとり、【目的語(相手)にアクションを起こさせる】という意味を表します。
例文:
- I made him clean the room.
(私は彼に部屋を掃除させた) - I had him fix my computer.
(私は彼にコンピューターを直してもらった) - I let him use my phone.
(私は彼に私のスマホを使わせてあげた)
どれも「彼に何かをやらせる」構文ですが、ニュアンスが微妙に違うことに注目してください。
3つの使役動詞のニュアンスの違い
ここでは、make / have / let がそれぞれどんなイメージ・ニュアンスをもって相手に行動を起こさせるのか、もう少し掘り下げてみましょう。
単なる「~させる」だけでは見えてこない、相手との力関係 や 相手の意思 がどれくらい尊重されているかなど、英語でコミュニケーションを取るうえで重要なポイントとなる部分をリッチに解説します。
使役動詞makeのニュアンス
核となるイメージ:
- 強い働きかけ・強制力
- 相手を「強制的に」行動させる、あるいは「~せざるを得ない状況に追い込む」印象。
使用シーンの例:
- My boss made me work overtime.
上司に「やれ」と強く指示され、嫌々でも残業しなくてはならなかった状況を想起させる - The teacher made the students rewrite their essays.
先生が生徒たちに「やり直しなさい」と命じているため、生徒の意志があまり反映されない。
補足・ニュアンスの深掘り:
「make」は「強要」というほど強い響きになることもあれば、単に「そういう流れだからやらせた」という程度のニュアンスにもなり得るなど、文脈によって強制の度合いに幅があります。
ただし「have」や「let」と比べて、相手の自由意志があまり尊重されていない という点が特徴です。何らかの「プレッシャー」や「拒否しづらい状況」が含意されることが多いでしょう。
使役動詞haveのニュアンス
核となるイメージ:
- 依頼・指示、または仕事として任せる
- 「こういう仕事があるからお願いします」「こういうタスクを割り当てるから取りかかってほしい」という場面で使われることが多い。
使用シーンの例:
- I’ll have my assistant book your flight.
アシスタントに「フライトを予約する」任務を割り振る。自然なビジネスオペレーションで、「頼む」「担当してもらう」感覚。 - I had the plumber fix the faucet.
水道工事業者に「蛇口を直してもらった」という頼みごと。相手は専門家で、修理するのが合理的という状況。
補足・ニュアンスの深掘り:
- 「have」は「仕事や役割を割り当てる」のに近いイメージで、「make」のような強制感は弱めです。
- ただし「依頼・指示」という意味では、どちらかというと話し手のほうが 上位の立場(お金を払う人・上司など) にいることが多く、命令というよりも「やってほしいことをお願いする」感覚に近い場合がほとんどです。
- ビジネスシーンでは I’ll have someone contact you.(担当者に連絡させます)のように使えば、とても自然かつ丁寧な言い回しになります。
使役動詞letのニュアンス
核となるイメージ:
- 許可を与える(相手の行動を認める)
- 相手がすでに「~したい」「~する必要がある」などの動機を持っている前提で、「やっていいよ」とゴーサインを出す感じ。
使用シーンの例:
- My parents let me stay out late on weekends.
週末は遅く帰ってきてもいいよ、と両親が許可している。子どもとしては「夜遅くまで遊びたい」という欲求があり、それを親が認めている状況。 - He let his dog run freely in the park.
犬に自由に走らせる許可を与えている。犬は走りたがっており、主人がそれを制限しないイメージ。
補足・ニュアンスの深掘り:
- 「let」には、「相手が本来自由意志でやりたいと思っていることを、制限せずに認める」という要素が含まれます。
- そのため、肯定文なら「相手が実際に行動を起こしやすい」雰囲気を帯びます。
まとめ:同じ「~させる」でも、誰がどんな意図で動かすかがカギ
- make は「強制的に相手を動かす」
相手はあまりやりたくないが、やらざるを得ない状況(相手の意思は尊重しない)。 - have は「仕事や任務として相手にやってもらう」
ビジネスや日常のタスクを自然な形で「頼む・指示する」イメージ。 - let は「相手の行動を許可する」
相手がやりたいことをやらせてあげる(認める)という姿勢。
こうした違いを把握しておくと、英語の会話や文章でより正確に「どのように相手に行動させたのか」を伝えられます。とくに 相手の自由意志がどれくらい尊重されているか、あるいは 行動を促す方法が“命令”なのか“依頼”なのか“許可”なのか を意識すると、ニュアンスのズレを減らし、ワンランク上の英語表現を使いこなせるようになるはずです。
使役動詞の使い分け練習:短い会話文やシチュエーション別例
さて、ここまで make, have, let のそれぞれの特徴を見てきましたが、「実際の会話やシチュエーションでは、どのように使い分ければいいの?」と気になる方もいるでしょう。
ここでは、ビジネス・家族・友人など、身近な場面ごとに短い例文を用意してみました。3つの使役動詞が、どんな状況で自然に使われるかをイメージしながら読んでみてください。
ビジネスシーン
上司が部下にタスクを割り当てる場合
- The manager made him finish the report by noon.
(上司が彼に、昼までにレポートを終わらせるよう強く指示した)
- The manager had him finish the report by noon.
(上司が彼に、昼までにレポートを終わらせるよう割り当てた)
ビジネスライクにタスクを振った印象で、自然な「仕事の依頼」のニュアンス。
- The manager let him finish the report by noon.
(上司が彼に、昼までにレポートを終わらせることを許可した)
クライアントとのやりとり
- We’ll have our customer support team contact you soon.
(まもなくカスタマーサポートから連絡させます)
have はビジネスメールなどでよく使われる自然な表現で、強制感は薄く、依頼のニュアンスがあります。make / let はあまり出番がないかもしれません。
家族のシーン
親子関係
make:
- My mom made me clean my room before dinner.
(夕食前に部屋を掃除するよう、母に強く言われた)
強制力があり、子どもが嫌がっていてもやらざるを得ない状況をイメージさせます。
have:
- My mom had me clean my room before dinner.
(夕食前に部屋を掃除するよう、母に頼まれたり指示された)
ビジネスほどフォーマルではないものの、「やってもらう」という自然な依頼やルールに従う感覚が強いです。
let:
- My mom let me watch TV after I cleaned my room.
(部屋を掃除し終わったら、テレビを見ていいよと母が許可した)
相手の意志や望みを認めてあげるニュアンスがあり、「やりたいことをOKにしてあげる」イメージです。
兄弟姉妹・ペットとのやりとり
make:
- My brother made me tell him where I hid his game.
(兄にどこにゲームを隠したか強制的に白状させられた)
嫌がっていても逆らえない、という強い押しつけ感があります。
have:
- I had my sister help me with my homework.
(宿題を手伝ってもらった)
頼む・お願いする形で、自然にやってもらうイメージです。
let:
- I let my sister borrow my laptop.
(妹がノートPCを使いたがったので、貸してあげた)
相手が希望する行動を認めてあげる「許可」のニュアンスが強いです.
友人とのシーン
一緒に行動する・遊ぶ場合
make:
- He made me go to the party even though I didn’t want to.
(行きたくなかったのに、無理やりパーティーに連れて行かれた)
相手の意思に反して行動を起こさせており、強制感がはっきりしています。
have:
- I had my friend pick up some snacks on the way.
(途中で友人にスナックを買ってきてもらった)
お願いや簡単な役割分担の感覚で、「ちょっとやっといて」と頼む場面によく使われます。
let:
- I let my friend drive my car.
(友人が車を運転したがったので、運転させてあげた)
相手のやりたいことを許可している状況。フレンドリーに「OK、どうぞ」というニュアンスです。
共同作業・プロジェクト
have:
- I’ll have you handle the design part, and I’ll do the coding.
(あなたにデザイン担当をお願いして、私はコーディングをやるね)
自然な役割分担やタスク割り当てのニュアンス。強制とは違い、協力し合う雰囲気です。
let:
- I let him take the lead in planning the event.
(彼がイベントの企画をリードしたいと言うので、やらせてあげた)
自主性を尊重して、相手に主導権を与えるイメージが「let」には含まれています。
make:
- He made me plan the whole event even though I had no idea about it.
(何もわからないまま、イベントの企画を全部やるよう無理やり言いつけられた)
ここでの「make」はかなり強い強要をイメージさせるため、友情関係ではあまり起こりにくい状況かもしれません。
まとめ:シチュエーションで見極める
- make:相手が嫌がっている、または気乗りしていない行動を「やらせる」ようなイメージ。
- have:自然な流れ・仕事・お願い事として「やってもらう」感覚。
- let:相手が望む行動に「OK」を出し、自由を与えるニュアンス。
日常会話やビジネスなど、どんな状況でも「相手の意志」と「行動を起こさせる側の権限・動機」がどうなっているかを意識すると、使い分けがよりスムーズになります。
注意したいポイント・よくある間違い
動詞の形に注意:to 不定詞はつけない
ポイント: 使役動詞である make / have / let は、動詞の原形 を後ろに続けるのが基本ルールです。
- (正)I made him do it.
(誤)I made him to do it. - (正)I had her check the schedule.
(誤)I had her to check the schedule. - (正)I let them stay here.
(誤)I let them to stay here.
文法的にも「to 不定詞」は使えないため、必ず動詞の原形を取る と覚えておきましょう。
「help」は“to”があってもなくてもよい
ポイント: よく似た文型を持つ動詞に help がありますが、こちらは to 不定詞 を使っても、動詞の原形 だけでもOKです。
- He helped me wash the dishes.
- He helped me to wash the dishes.
両方とも意味はほとんど変わりません。help は「手伝う」「助ける」という意味であり、make / have / let のような「相手を動かすニュアンス」とは少し異なる動詞です。
「force, allow, permit, get」など類似表現との違い
force:
- He forced me to stay late. (make よりも強い“無理やり”のニュアンス)
使い方は force + 目的語 + to 不定詞。
allow / permit:
- He allowed me to stay late.
- He permitted me to stay late.
構文は allow/permit + 目的語 + to 不定詞。let とほぼ同じ意味ですが、ややフォーマル です。
get:
- I got him to fix my bike. (何とかお願いして直してもらった)
こちらも get + 目的語 + to 不定詞 をとり、「説得してやってもらう」ニュアンスが含まれます。
よくある混同例
- make と force: どちらも強制だが、force のほうがさらに強い意味を持ち、文法的には to 不定詞 を使う。
- let と allow: どちらも「許可」。allow のほうがフォーマルで、文法的には to 不定詞。
ミスを防ぐためのコツ
- 構文パターンを暗記する: make / have / let は「動詞の原形」、force / allow / permit / get は「to 不定詞」。
- 誰が行動の主体なのか確認する: 自分が強要しているのか、依頼しているのか、相手のやりたいことを許可しているのかを考える。
- 場面別フレーズを覚える: ビジネスシーン・日常会話など、実際に使いそうな例文をストックし、自然と使えるようにしておく。
肯定文では「実際に行動が行われた」ことを含意する
ここからは少し言語学的なお話。意味の世界をご案内します。
肯定文の場合、「~させた」と言うからには、基本的に相手がその行動を実際に行ったことを前提とする表現です。たとえば、
- I made him do his homework. → 「やりたがらなかったが、強制してやらせた」
- I had him do his homework. → 「私は彼に宿題をするよう頼んだ/指示した(結果、彼はした)」
- I let him do his homework. → 「宿題をやりたがっていた(あるいは必要があった)ので、私はやらせてあげた」
いずれも「宿題は最終的に行われた」というエンドポイントが含意されており、下記のようなbut以下でエンドポイントの結果を打ち消すことはできません。
- *I made him do his homework, but he didn’t do it.
- *I had him do his homework, but he didn’t do it.
- *I let him do his homework, but he didn’t do it.
上記のように先頭に「*」が付いているのは、その例文が文法的・意味的に不適格であることを示す言語学の慣例的記号です。
発展編:否定形になるとどう変わる?
このように、使役動詞make,have,letはニュアンスこそ違うものの、肯定文では「相手に~させる」という共通点を持ち、「最終的にやった」という意味を含む点で共通です。
しかしながら、否定文にすると、これら3つの使役動詞の意味合いが大きく変わってくるのです。
下記の記事で、それぞれの使役動詞を「否定形」にしたときの意味の違いと、そこに潜む言語学的背景について掘り下げます。
【豆知識】使役動詞を否定文にしたときの振る舞いを言語学的に分析する
全体のまとめ
ここまでご覧いただきありがとうございます。
3つの動詞はどれも「~させる」と訳されますが、相手との関係性や相手の意志をどれだけ尊重するかで、選ぶべき表現が変わります。
無意識に「強制」している印象を与えたり、「許可」のニュアンスを伝え損なったりしないよう、場面や相手の気持ちを考えつつ、使い分けを意識してみましょう。
再度ポイント整理:
- make:強制寄り(相手が嫌がっていてもやらせる)
- have:依頼・指示寄り(仕事や役割として自然にお願いする)
- let:許可寄り(相手がやりたがっていることを認めてあげる)
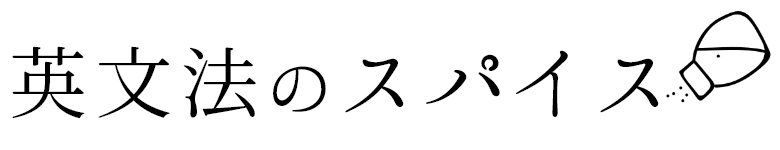
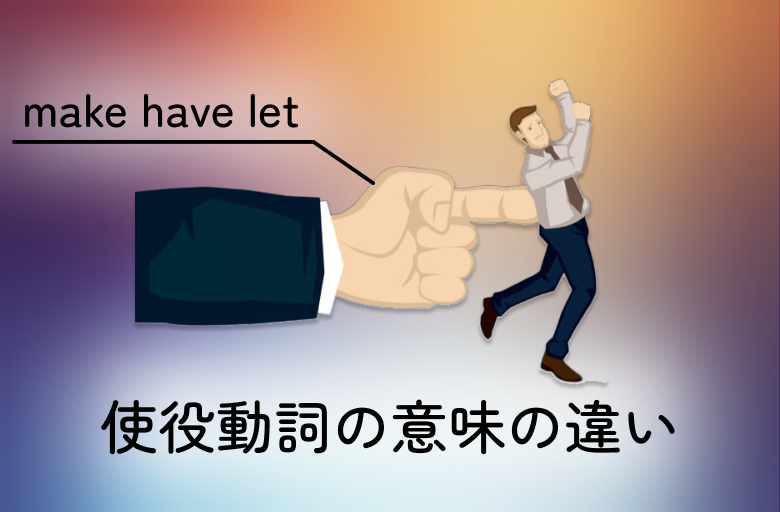

コメント